当店にいらっしゃる方の中では、頭痛を主訴として治して欲しいという方以外でも頭痛持ちの方がいらっしゃり、頭痛の頻度や痛さなどは程度の差こそあれ多くの方が頭痛に悩まされている印象があります。
実際に日本においては、15歳以上の人における慢性頭痛の有病率は約40%とされています。
計算すると日本の頭痛人口は約4,000万人いると推定されています。
かくいう私も頭痛が起きやすく、特に気温が高い日や反対にすごく寒い日に頭痛が生じやすい傾向があります。
しかし、よっぽどではない限り頭痛の治療で病院を受診する人は少なく、鎮痛剤でやり過ごしている方が多いのが現状です。
頭痛はさまざまな要因で発症しますが、今回は夏に生じやすい頭痛を5つに分けてご紹介します。
また、それぞれの頭痛のタイプに対してどのような漢方治療を行うのかについても考察してみたいと思います。
①暑さによる頭痛
②太陽の光刺激による頭痛
③脱水状態による頭痛
④冷房による頭痛
⑤気圧変動による頭痛
①暑さによる頭痛
気温が高いと、体に熱を持ちます。
体が熱くなったら血管を拡張することで、血流をよくして皮膚から熱を発散させます。
*反対に、寒いは血管が収縮して血流を減らすことで体の熱を逃さないようにしています。
暑い日は血管が拡張するので、広がった血管が脳神経が刺激しその結果頭痛が生じます。
頭痛もちの人は頭に熱をもちやすい傾向にあり、熱をもつと頭が痛くなります。
このような方は、意図的に熱を冷ますようにしなければなりません。
特に首の太い血管のあたりやおでこなどを冷やすと効果的です。
暑さによる頭痛の漢方薬治療
漢方では暑い夏の日は「暑邪(ショジャ)」と呼ばれる、外邪が体に影響を及ぼすと考えます。
真夏の暑い日に長時間外で活動したり、出歩いたりすることで、暑邪の影響を受けることになります。
熱中症も暑邪に該当して、体に熱がたまり脱水となることで発症します。
暑邪による頭痛の場合は、体の熱を冷まし拡張した血管を鎮める漢方薬を用いることで頭痛を改善させます。
一方で、慢性的に暑邪や熱邪を繰り返す場合は、体のぐったり感や倦怠感などが生じます。
この場合は、身体の弱りが生じているので身体の元気を補いながら、熱を冷ます治療を行なっていくことで頭痛の発生を予防します。
②太陽の光刺激による頭痛
夏場は光の刺激が強くて、目に入ってくる光で眩しさを感じることが多いです。
特に片頭痛持ちの方は、光の刺激に反応しやすく、頭痛が発生しやすいです。
光による刺激の頭痛を特に光過敏性頭痛と呼びます。
他にも偏頭痛持ちの方は音や匂い、気圧でも頭痛が発生しやすいと言われています。
強い光は、目から入り脳に刺激が伝わり、視神経や脳の血管を強力に刺激することで頭痛を引き起こします。
太陽光による頭痛対策としてはサングラスをかけることです。
サングラスのレンズの色は真っ黒すぎる目の瞳孔が開くので、薄緑色がよいとされています。
私も以前は真っ黒いレンズを使っていましたが、今年から薄緑色に変えてみました。
*まだ使い始めでなので、効果は分かりません。
太陽光による頭痛の漢方薬治療
光刺激により脳が過剰に興奮状態にあるので、その過剰な興奮を鎮静させる必要があります。
この場合、太陽光の刺激だけでなく夏特有の熱邪(暑邪)も加わっているので、脳の興奮は「熱」によると考えられます。
そこで、治療の方針としては、暑邪と同様に脳の過剰な熱を冷ます(清熱)させる漢方薬が有効と考えられます。
③脱水状態による頭痛
暑い場所にいると、すぐに汗が出てしまい知らないうちに脱水状態になってしまいがちです。
脱水状態になると、体内の水分不足により血液の循環が悪くなり、脳への酸素や栄養の供給が減少することで頭痛が発生します。
夏場はのどの渇きを意識する前に、こまめな水分補給をとることが大切です。
その際、冷たい飲料を一気に飲まないことが大切です。
冷たい飲み物を一気に飲むと胃腸がびっくりしてしまい、消化がうまく働かず水分が適切に吸収されなくなるからです。
理想は常温の水を、ちょびちょびと喉にしみわたらせるようにして飲むことです。
とはいえ、暑い季節には冷たいものを取りたくなるので、その場合でも少しずつ飲むように心がけましょう。
脱水状態による頭痛の漢方薬治療
この場合は2つのパターンが想定されます。
1つ目は暑邪による熱が激しく、その結果脱水となってしまう場合です。
この場合は暑邪の漢方薬治療を行うことで、熱が除かれ結果として脱水も解消されます。
もう一つは、脱水だからといって過剰に水分をとってしまい、それでも口の渇きが治らない場合です。
この場合は、のどの渇きは満たされず、さらに胃腸は水でチャポチャポになってしまっています。
この場合は水分代謝を改善する漢方薬を用いることで、停滞した水を巡らせて血液中に水分を行き渡らせることで頭痛を軽減させることができます。
④冷房による頭痛
これまでは暑さによる頭痛をメインでご紹介してきました。
一方で、冷房あたりすぎることでも頭痛は発生します。
冷房で体が冷えすぎると筋肉が緊張し、血行不良を起こし頭痛となることがあります。
とりわけ1日中家やオフィスにこもって仕事をして、ほとんど外に出ることはないので、体はガチガチに冷えて筋肉が固まってしまったことで頭痛となるパターンです。
このような方は、頭痛として痛み止めの薬(鎮痛剤)を使うのはお勧めしません。
鎮痛剤は炎症を抑えるための成分が入っていますが、同時に解熱作用ももちあわせています。
その結果、体が冷えたことで起こる頭痛(緊張型頭痛)の場合、鎮痛剤を服用することでより一層身体の冷えを助長してしまう可能性があります。
緊張型頭痛の場合はお風呂に入って体を温めたり、体を動かすことでこり固まった筋肉を解きほぐすことが効果的です。
冷えによる緊張型頭痛の場合はぜひ試してみてください。
冷房による頭痛の漢方薬治療
冷房による頭痛の場合は、明らかに冷えが原因となっています(寒証)。
ですので、冷えを追い出し、身体を温めて、血流を改善する漢方薬を用います。
⑤気圧変動による頭痛
頭痛持ちの方に多いのが、気圧変動による頭痛です。
これは夏場よりも梅雨の季節に起きやすですが、夏場は急な激しい雨や台風などが発生することがありますので、気圧変動の影響を受けやすいといえます。
急激な気圧の変化によって、自律神経が乱れ交感神経が活性化します。
これにより、頭痛が発生します。
また、夏場は湿度が高くなりやすく、湿度が70%以上になると体温調節のための汗が蒸発できなくなります。
これにより体内に熱がこもることでサウナのような状態となり、脳の血管が拡張し片頭痛も起き安くなります。
気圧変動による頭痛の漢方薬治療
気圧変動による頭痛には「湿度上昇」と「気の流れの変動」という2つの対策が必要です。
詳しくは「気象病の漢方薬治療」をご覧ください。
具体的にいうと、「湿邪」と「気滞・気の上衝・気逆」を改善させる漢方薬を組み合わせることで治療を行います。
まとめ
以上が夏に起きやすい頭痛の原因と漢方薬での対策方法について、私見を交えて解説をしました。
もちろん、漢方薬は個々人に合わせて用いますので、ここに挙げたものではない漢方薬の選択方法も多数存在するかと思います。
「頭痛だから○○という漢方薬」を使うというわけではありません。
夏の漢方薬としては「五苓散」が有名ですが、この漢方薬が適応となるのはあくまでも数ある状況の一部に過ぎません。
気象病の頭痛やめまいに多用されていますが、実際に効かない方もいらっしゃいます。
そのような場合にも、漢方的な視点で正しく見れば別の解決策が見つかる場合もございます。
もし、頭痛の治療を行なっていて満足な結果が得られない場合は漢方専門の医療機関にぜひご相談ください。
関連記事
あわせてご覧ください。








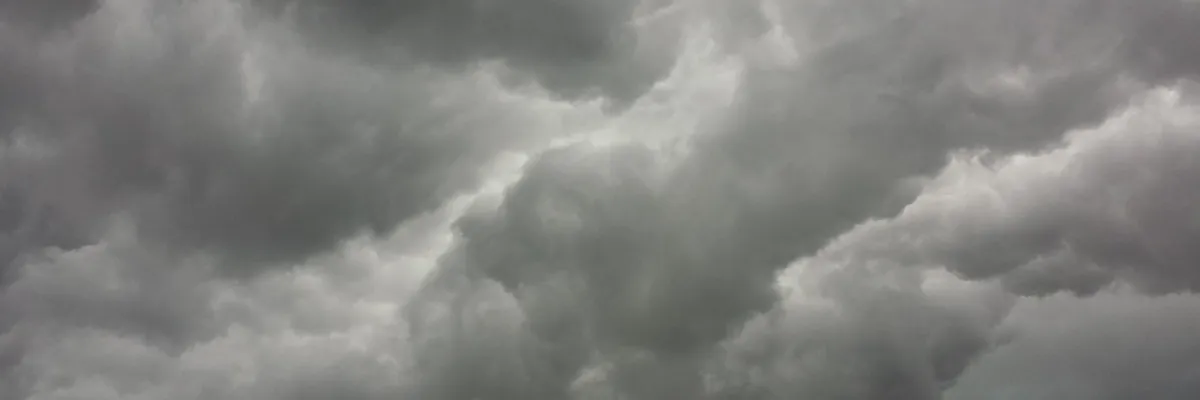
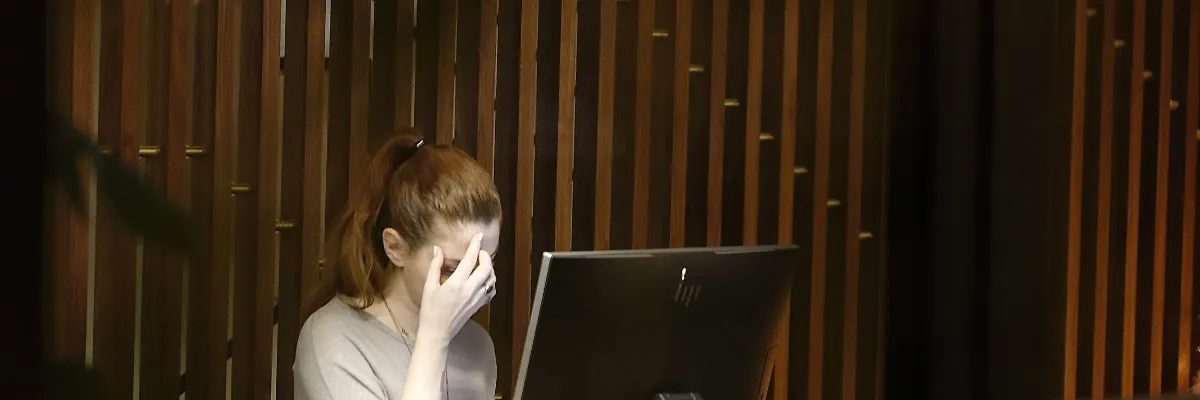
コメント