*この内容はstand.fmでも放送しています。
頭痛でお困りの方は多く、3,000万〜4,000万人くらいいると言われています。
ですが、頭痛への対処法としては鎮痛剤を用いてその場をやり過ごしている方も多くいらっしゃいます。
東洋医学では単に痛みを止めるのではなく、東洋医学的な原因を探って個々人の体質に合わせた漢方薬を使っていきます。
頭痛にもさまざまなタイプがありますが、胃腸が原因となって発症しているケースも少なくありません。
現に、「呉茱萸湯(ゴシュユトウ)」・「半夏白朮天麻湯(ハンゲビャクジュツテンマトウ)」・「五苓散(ゴレイサン)」などの頭痛によく用いる漢方薬は胃腸の不調を改善させることで、頭痛を軽減させています。
東洋医学では胃腸はとても大事な臓腑で、どのような病気の相談であっても胃腸の状態を確認します。
「頭痛の漢方薬治療」について、詳しくはこちらをご覧ください。
胃腸が悪いとなぜ頭痛が起きるのか
胃腸の働きが悪くなると、せっかく摂った飲食も十分に消化吸収されません。
適切に処理されなかった飲食は、体にとって不要な水(これを痰飲(タンイン)や水毒(スイドク)と呼びます)になります。
この痰飲は身体のいたるところに停滞し、さまざまな症状を引き起こします。
・ベタつき(体に停滞して容易にとれない)
・重い(停滞した部位に重だるさを感じる)
・胃:吐き気・胃もたれ・食欲不振
・腸:下痢・腸がゴロゴロ
・経絡:しびれ・痛み
・皮下:むくみ
・頭:頭痛、めまい、耳鳴りなど
こういった痰飲はさまざまな原因で発生しますが、その一つが胃腸の不調によるものです。
胃腸で生じた痰飲が上部に移行することで、頭に痰飲が停滞し、頭の重だるさや神経圧迫による頭痛、めまいなどを引き起こすことがあります。
こういった場合、本来の頭痛が生じている頭部を改善するのではなく、胃腸の働きを整えることで痰飲を減らし、頭痛の要因をなくしていく治療を行なっていきます。
頭痛でお悩みの方は胃腸を整えることで、根本的な改善につながる事があります。
とりわけ、食事は胃腸の働きに直接関係するので、食生活の改善はとても大切なことになります。
特に痰飲はベタつきのあるもの(油っこい食事・甘いもの)や胃腸の働きを鈍らせる冷えた料理(サラダ・刺身・アイスクリームなど)を取りすぎないようにしてみてください。
また、過度な食事も避けて、腹八分目で抑えることも大切です。
これだけで頭痛がなくなるわけではないかもしれませんが、痰飲の発生を抑える事ができます。
本格的に頭痛の治療をご希望の方は、ぜひ漢方専門の医療機関にご相談ください。








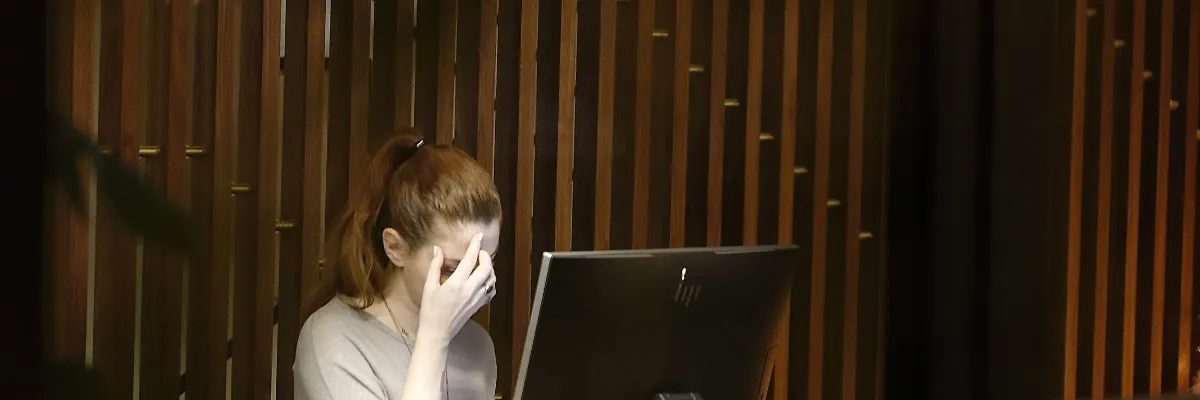
コメント